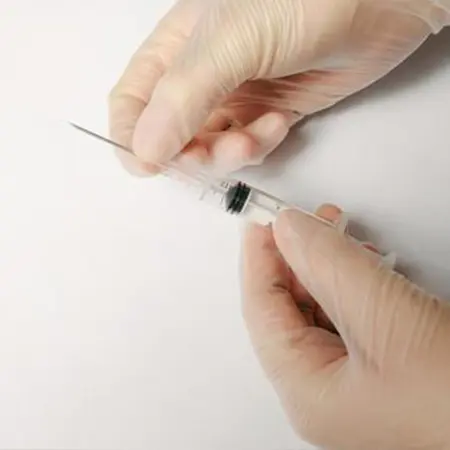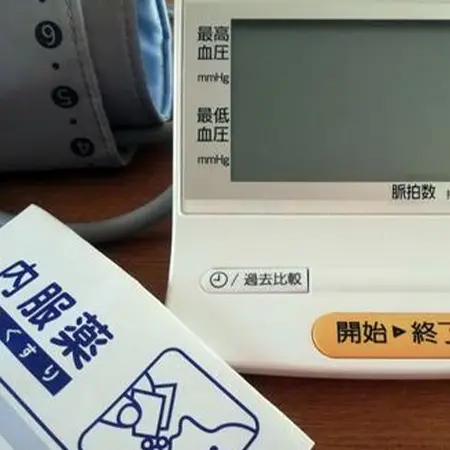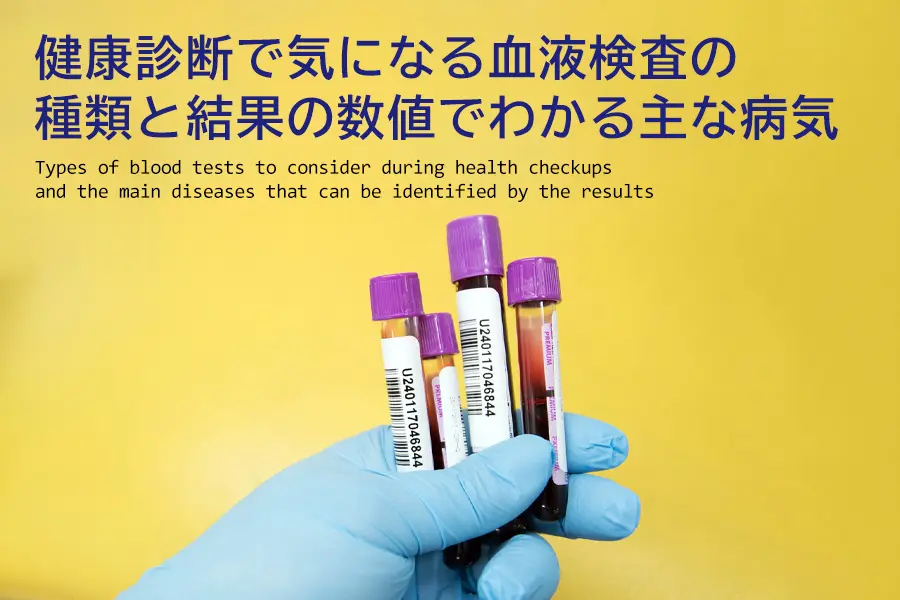健康診断で行う血液検査には、体の異常や病気の兆候を見つける重要なヒントが隠されております。血液検査は、体の中の状態を“見える化”する大切な検査で病気の早期発見や生活習慣の見直しにも役立ちます。
ここでは、検査項目ごとの種類や数値の意味、どんな病気と関係があるのかをわかりやすく説明しています。肝機能・腎機能・血糖・コレステロールなど、よく行われる検査を中心に異常値が示すリスクや再検査の目安についても詳しく紹介しています。
Contents
スポンサーリンク
▼ 血液検査とは?
血液中の成分を測定して健康状態や臓器の働きを調べるための検査のこと

血液検査は採血だけで多くの情報が得られることから、健康診断や人間ドック、病院での診察時にも広く用いられております。検査で得た情報を数値化し、体のさまざまな不調や疾患の兆候を読み取ることができます。
血液検査の目的
血液検査の主な目的は、血液中に含まれる赤血球・白血球・血小板などの血球成分や、栄養素、酵素、ホルモン、老廃物などを検査し、体の健康状態や病気の有無を調べることです。
血液検査は「予防」「診断」「治療」のすべての段階で活用される非常に重要な検査になります。
血液検査で確認する内容は下記の通りです。
| 健康状態の確認 |
|---|
| 日々の生活習慣による体の変化や、加齢に伴う機能の低下をチェックするために行われます。 |
| 病気の早期発見 |
|---|
| 自覚症状が出る前の段階でも、数値の異常により、病気の兆候を見つけることができます。 |
| 治療の効果や経過の確認 |
|---|
| 薬の効果や病状の進行具合を把握するために、定期的な検査が行われることもあります。 |
血液検査の数値について

血液検査の結果には、各項目ごとに基準値(参考値)が設定されております。この基準値の範囲内に収まっていれば健康上問題はないと言われておりますが、年齢・性別・体質などにより個人差があるため、一概に異常があるとは言い切れない場合もあります。
また一度の検査で判断できない場合には、再検査が行われることがあります。数値が高い・低いだけで一喜一憂するのではなく、全体のバランスや医師の所見と合わせて判断することが大切です。
検査項目別 参考(基準)値一覧表
| 検査項目 | 略称 | 主な役割 | 基準値の目安 | 基準値外で疑われる病気 |
|---|---|---|---|---|
| 赤血球 | RBC | 酸素を運ぶ | 男性:430〜570 万/μL 女性:380〜500 万/μL |
貧血、脱水症など |
| 白血球 | WBC | 免疫機能 | 4000〜9000 /μL | 感染症、白血病など |
| AST | GOT | 肝酵素 | 10~40 U/L | 肝炎、脂肪肝など |
| ALT | GPT | 肝酵素 | 5~45 U/L | 肝障害など |
| HbA1c | ー | 血糖平均 | 4.6~6.2 % | 糖尿病など |
※表はChat GPTで生成。
▼ 主な血液検査の種類
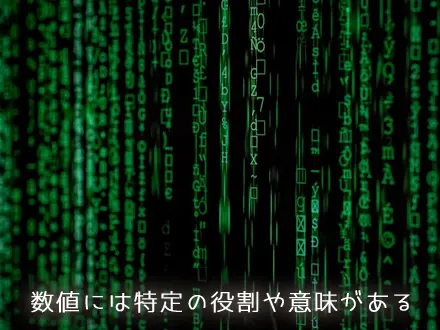
血液検査では様々な項目を調べることができますが、それぞれの数値には特定の役割や意味があり、異常値は特定の病気や体の異変を示すサインとなります。
健康診断でよく行われる代表的な血液検査の種類と、それぞれからわかる病気については次の通りです。
▽赤血球・白血球・血小板(血球系)
血液の成分である赤血球・白血球・血小板は、体内の酸素運搬・免疫・防御機能・止血などに関わりがあります。
| 赤血球(RBC) | 少ないと貧血、多すぎると脱水症状や血液濃縮が疑われます。 |
|---|---|
| 白血球(WBC) | 増加は感染症や炎症、極端に多い場合は白血病の可能性もあります。減少は免疫低下を示すこともあります。 |
| 血小板(PLT) | 出血を止める働きです。低下すると出血しやすく、高すぎると血栓のリスクがあります。 |
▽肝機能検査(AST/ALT/γ-GTPなど)
肝臓の働きを確認する検査です。アルコールの影響や肝疾患のスクリーニングに使われます。
| AST(GOT) |
肝細胞が壊れると血中に漏れ出す酵素です。数値が高いと肝炎や脂肪肝などの疑いがあります。 |
|---|---|
| γ-GTP | アルコール摂取の影響を受けやすく、飲酒習慣が強いと高値になりやすいです。肝胆道系の障害も示唆されます。 |
| ALP・LDH | 胆道や骨、他の臓器の状態を示すこともあります。 |
▽腎機能検査(クレアチニン/eGFR/BUN)
腎臓が老廃物をきちんと排出しているかを調べます。慢性腎臓病の早期発見に有効です。
| クレアチニン(Cr) | 腎臓で排出される老廃物です。上昇すると腎機能低下の可能性があります。 |
|---|---|
| eGFR | 腎臓のろ過能力を示す推定値です。数値が低いと慢性腎不全が疑われます。 |
| BUN(尿素窒素) | 腎機能低下や脱水状態を示唆することがあります。 |
▽脂質・血糖関連(LDL/HDL/中性脂肪/血糖値/HbA1c)
生活習慣病との関係が深い項目です。動脈硬化や糖尿病のリスク評価に使われます。
| LDL (悪玉コレステロール) |
動脈硬化や心疾患のリスクを高めてしまいます。 |
|---|---|
| HDL (善玉コレステロール) |
血管内の余分な脂質を回収する役割があります。少ないとリスクが上昇します。 |
| 中性脂肪(TG) | 高すぎると脂質異常症の可能性があります。 |
| 血糖値・HbA1c | 高値が続くと糖尿病が疑われます。HbA1cは過去1~2ヶ月の血糖の平均を反映します。 |
▽炎症や感染のサイン(CRP/ESRなど)
体内に炎症や感染が起きていないかを調べる項目です。
| CRP(C反応性タンパク) | 炎症の程度を数値化します。高値なら細菌感染やリウマチ性疾患の可能性があります。 |
|---|---|
| ESR(赤沈) | 炎症の有無をゆるやかに反映します。慢性疾患でも上昇します。 |
▼ 血液検査の結果でよくある疑問
正常値と人による違い

血液検査の結果には、それぞれ基準値(正常値)が設定されておりますが、この値はすべての人に当てはまるわけではありません。基準値とは、健康とされる多くの人の平均的な数値をもとに設定された参考範囲です。
そのため、年齢・性別・体格・体質、さらには体調や生活習慣によっても数値には個人差があります。例えば運動習慣のある方は筋肉量が多いためクレアチニンが高めに出ることがあります。また、女性は生理周期により血球系の数値が変動することもあります。
基準値からわずかに外れている場合、必ずしも異常や病気があるとは限りません。そのため医師による総合的な判断が重要となります。
再検査と受診の目安
要再検査と記載されている場合は、必ずしも重大な病気があるというわけではありません。以下のような理由で再検査が必要とされる場合があります。
- ●一時的な体調変化(睡眠不足、脱水、ストレスなど)による数値の乱れ
- ●薬の影響や検査当日の食事・運動が反映された結果
- ●明らかな異常はないが変動傾向を確認するための経過観察
再検査の案内があった場合は、できるだけ速やかに医療機関を受診し必要に応じて精密検査や他の項目との照らし合わせを行うことが望まれます。また、自覚症状がある場合や数値の異常が大きい場合には、早めに受診をして健康状態を把握し、必要に応じて治療を行うようにしましょう。
▼ 血液検査前に気をつけること
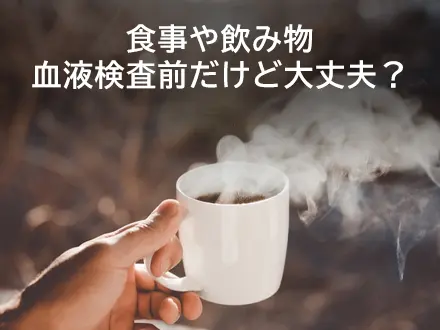
血液検査の結果を正確に反映させるためには、検査を受ける前の過ごし方や行動にも注意が必要です。特に健康診断や人間ドックなどで行われる血液検査では、事前の準備が数値に影響を与えることがあります。
押さえておきたいポイントは下記の通りです。
食事と飲み物の制限
多くの血液検査では前日の夜から絶食を求められる場合があります。特に血糖値や中性脂肪、肝機能などの検査においては、食事の影響を受けやすいためです。
- 検査前8~10時間は食事を控えるのが一般的です(※水は摂取可)。
- 甘い飲み物、カフェイン、アルコールも影響を与える可能性があります。
- 検査前に指定がある場合は、それに従うことが大切です。
薬の服用について
普段飲んでいる薬やサプリメントが検査結果に影響を与えることがあります。
- 検査前に服薬して良いかどうかは、事前に医師または看護師に確認しておきましょう。
- 糖尿病や高血圧、コレステロールに関する薬は影響が出やすい項目です。
過度な運動・睡眠不足を避ける
激しい運動や極端な睡眠不足も血液の成分に一時的な変化をもたらすことがあります。
- 検査前日はできるだけリラックスして過ごすよう心がける。
喫煙・飲酒は控える
検査前の喫煙や飲酒も血圧や血糖値、肝機能の数値に影響を与える可能性があります。
- 検査前日は喫煙・飲酒を控えるようにする。
血液検査前の行動や生活習慣は結果に大きく関わります。医療機関の指示に従い、適切な準備を行うようにしましょう。
▼ まとめ

血液検査は、体の中の状態を客観的に把握できる非常に有用な検査です。健康診断や人間ドックで行われる検査項目には、赤血球や白血球といった血液成分のほか、肝機能・腎機能・血糖・脂質・炎症反応など様々な項目があります。
検査前の食事や服薬など、生活習慣に気を配ることでより正確な結果が得られます。結果をもとに医師からのアドバイスを実践することで、病気の早期治療や予防にもつながります。ご自身の健康状態を知るために、血液検査の意味や結果の見方を正しく理解し日々の健康管理に役立てていきましょう。